
中2理科「化学変化」だれでもわかる!化学反応式のつくり方
中2理科の「化学変化」で学習する「化学反応式のつくり方」の解説記事です。①元素記号と化学式のおさらい、②化学反応式のつくり方、③代表的な化学反応式について詳しく説明しています。特に酸化銀の分解や銅の酸化など、中学で学習する基本の化学反応式を5つほど詳しく解説していますので、理科が苦手な中学生はぜひご覧下さい。
中学生の勉強に役立つ情報を発信しています

中2理科の「化学変化」で学習する「化学反応式のつくり方」の解説記事です。①元素記号と化学式のおさらい、②化学反応式のつくり方、③代表的な化学反応式について詳しく説明しています。特に酸化銀の分解や銅の酸化など、中学で学習する基本の化学反応式を5つほど詳しく解説していますので、理科が苦手な中学生はぜひご覧下さい。

中2理科の「化学変化」で学習する「元素記号と化学式」の解説記事です。①原子と分子、②元素記号と化学式、③単体と化合物について、それぞれ押さえておくべきポイントを詳しく説明しています。また、必ず覚えておく必要がある元素記号と化学式を紹介しています。理科が苦手な中学生はぜひご覧下さい。

中2理科の「化学変化」で学習する「炭酸水素ナトリウムの熱分解」「水の電気分解」の解説記事です。炭酸水素ナトリウムの熱分解と水の電気分解の実験で、押さえておくべきポイントを詳しく説明しています。また、それぞれの分解で発生する物質名を覚えるゴロ合わせも掲載しています。理科が苦手な中学生はぜひご覧下さい。
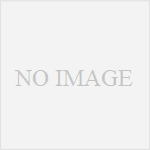
中1理科の「凸レンズの作図とできる像」についての解説記事です。凸レンズの作図で基本となる3パターンの光の進み方をわかりやすく説明しています。また、凸レンズでできる像を、像の大きさ・物体とレンズの距離・像とレンズの距離・像の向きの4つのポイントでで詳しく解説しています。理科が苦手な中学生はぜひご覧下さい。

中1理科の「光の屈折」についての解説記事です。「屈折」とは、光が透明な物質どうしの間を進むとき、境界面で折れ曲がる現象のことです。記事内では、空気から水・ガラスへ進むとき、水・ガラスから空気へ進むとき、光がどのように屈折するのかについて図解で詳しく解説しています。理科が苦手な中学生はこちらの記事をぜひご覧下さい。

中1理科で学習する「光の反射」について詳しく説明しています。①光の直進について、②「反射の法則」について、③反射において頻出の記述問題や作図問題の取り組み方について、それぞれ詳しく解説しています。また反射についての基本問題も掲載しています。理科が苦手な中学生はこちらの記事をぜひご覧下さい。

中1理科の「質量パーセント濃度」について詳しく説明しています。苦手意識を持っている中学生が多い水溶液の濃度を求める計算問題の解き方について、すぐに理解できるよう分かりやすく解説しています。また解き方を練習できるよう問題も掲載しています。理科が苦手な中学生はこちらの記事をぜひご覧下さい。

中1理科の「水溶液と再結晶」について詳しく説明しています。①「溶質・溶媒・溶液」②「溶解度」③「再結晶」について、それぞれ要点をわかりやすくまとめています。再結晶の2通りの方法については、特に詳しく解説しています。また重要語句を確認する問題もあります。理科が苦手な中学生は、こちらの記事をぜひご覧下さい。

中1理科の「状態変化と温度、蒸留」について詳しく説明しています。➀「沸騰」について、②「融点」と「沸点」について、➂「純粋な物質」と「混合物」のちがいについて、④「蒸留」について、それぞれ要点をわかりやすくまとめています。また、重要語句を確認する問題もあります。理科が苦手な中学生は、こちらの記事をぜひご覧下さい。

中1理科の「状態変化と質量・体積の関係」について詳しく説明しています。➀状態変化とは何か、②「固体⇄液体」に状態変化する場合、➂「液体⇄気体」に状態変化する場合について、それぞれ要点をわかりやすくまとめています。また、重要語句を確認する問題もあります。理科が苦手な中学生は、こちらの記事をぜひご覧下さい。